事例・コラム
Column
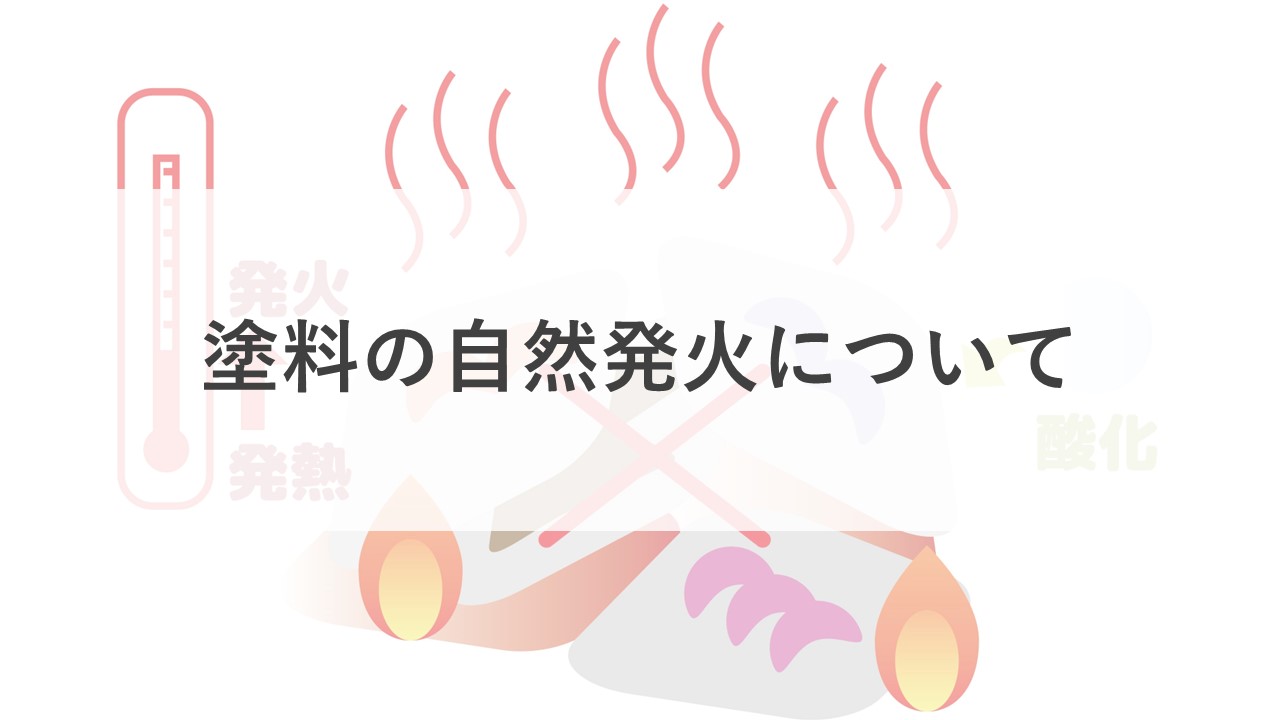
みなさんこんにちは!営業のKです。
今回のテーマは「塗料の自然発火について」です。
こちら、ご存じの方もいらっしゃると思います。
初めて聞いたという方の為にも、分かり易く説明していきますね。
目次
自然発火とは
まず、「自然発火」という現象についてですが、
人が火をつけていないのに自然に出火することを指します。
当たり前のことを申しておりますが、実際に起こりえることです。
どうして自然発火が起きるのかですが、
一般的に、揚げ物の油や塗料などの油類は、酸化(空気中の酸素と反応)する過程で発熱する性質があるからです。
とはいっても、単に油をボトルに入れて保管していたり、塗料を塗った面(塗面)が発火するわけではありません。
油や塗料が染み込んだ紙や布などを山積みしたり、ごみ袋にまとめて入れて放置するなどして熱がこもると、自然発火が発生することがあります。
では、塗料は全部、自然発火を起こす危険性があるのでしょうか?
答えはNOです。
自然発火する可能性のある塗料は、植物油からなる自然塗料(天然系塗料)や酸化反応で硬化し塗膜になる「アルキッド樹脂系塗料」です。(「油性塗料」や「弱溶剤系塗料」と呼ばれることが多い塗料ですね)
弊社塗料では、
等が該当します。
塗装シーンにおける自然発火事例
①オイルステイン(自然塗料)をふき取ったウエスによる自然発火
Aさんは住宅内装の塗装で、オイルステインを刷毛やローラーで塗装した後、ウエスでふき取る作業を行いました。
その時使用したウエスは、ブルーシートの上に山積みにしたり、空になった塗料容器にまとめて入れたりしていました。
その後、廃棄用の袋にまとめて別の作業をしていたところ、袋から煙が出ていることに気がつきました。
➡先に紹介した通り、ウエスに含まれた塗料が酸化・熱がこもって発火した、というケースです。
②アルキッド系樹脂塗料の研磨粉による自然発火
Bさんは体育館のフロアーを、酸化反応のアルキッド系樹脂塗料で塗装していました。
翌日、塗膜が乾燥した後に、ポリッシャーで研磨を行いました。
研磨によって生じた大量の研磨粉は、掃除機で吸い取って、ごみ袋にまとめていました。
しばらくすると、産廃置き場のごみ袋から煙が出ている、と別の業者から報せがありました。
➡塗料は乾いていたのに何故?と思われるかもしれませんが、このタイプの塗料は、塗装後数日、数週間たっても硬化(酸化反応)を続けていることがあります。
塗膜が研磨粉になった後も酸化反応により発熱し、それが一か所に密集して熱がこもった結果、発火した、というケースです。
対策
・塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨粉、スプレーダストなどは廃棄するまで必ず水につけておく。
この時、水が蒸発しないように容器に蓋をしておくなど注意が必要です。
特に、スプレーガンなどを用いて、乾式ブースなどで塗装する場合は、フィルターに塗料が堆積することになりますので、非常に危険です。
どうしても塗装する場合、塗装後は(場合によっては塗装中も)必ずフィルターの処置をしてください。
・廃棄する塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨粉、スプレーダストなどと一緒に、金属粉、錆びた鉄くぎなどを一緒に置かない。
化学反応により、酸化を促進させてしまう場合があり危険です。
・安全な焼却設備がある場合は、そこで焼却する。
塗装後の処理までしっかり熟知いただいて、安心・安全の塗装環境にしていきましょう。
不明な点や相談したいことがございましたら、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお声がけください。
★コラムの更新・ウェビナーの開催情報は、弊社メールマガジンにて随時配信しております。
ご登録を希望される方は、以下の登録フォームより、お気軽にお申込みください。

この記事を書いた人:営業 K
親しみやすい文章に定評のあるライター。業務では顧客への塗料の提案を担当。趣味は映画観賞(特にホラー)。3児のパパ。2025年1月に第三子(娘)が生まれ、育児奮闘中。家族みんなでキャンプに行くために、準備中。※キャンプギアを揃えて満足してしまっている、、、